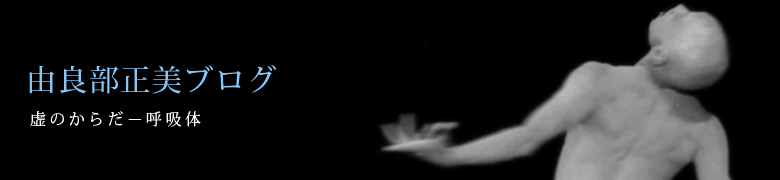今年の元立誠小学校跡で、行われたダンスファンフェアーのレクチャーを伴戸チカコさんが、テープから文字に起こしてくれました。長文なのに、頭が下がります。読んでみると、自分でもなかなか面白かったです。レクチャーも即興の踊りのように、その時一度きりしか表わせないものがあります。長いですし、レクチャーに参加していないと、なかなか伝わりにくい物もありますが、宜しければ!
舞踏をめぐるコトバとカラダ
伴戸:経歴から言うと、東方夜総会にいらっしゃって、その後、ソロで活動。私は舞踏を始めた時はとてもお世話になって、舞踏のワークショップ(WS)も長くやってはりますよね。何年くらいから?
由良部:25年くらい前かな。
伴戸:舞踏に出会ったきっかけというのは?
由良部: 確か19か20歳くらいの時だったと思います。僕、1958年生まれなんですね。その時代というのは、学生運動、対抗カルチャーというんですか、芸術的なものの変革期、熱い時代、その熱が冷めた時代かな。三無主義とか言われた。「無責任、無関心、無感動なやつらだ」みたいに言われてた時代。
僕は中央大学の理工学部だったんですよ。土木工学科で。だけど、どうもこのまま社会に出ていく自信がない。モラトリアムでしょうかね。どうして生きていこうみたいな感じで悩んでいた時に、なぜか急に演劇をやりたくなって。3回生の時に。それまで表現というものに関わってなかったんだけど。中央大学演劇研究会というのに急に入って、やったんだけど、僕の中で言葉がうまく出てこない。
エチュード、といって、ある設定をして即興的に言葉をかけあいしながらやっていくような練習があるのだけれど、そういうのが全然、自分に合わない。身体がバタバタする感じ。今こう話しているのも、あんまり苦手なんですけど。身体がバタバタしてくるような感じがあって。「お前、舞踏の方がいいんじゃないか」と言われた時に、舞踏って何だろうって。そんなくらいの情報しかなくて、そんな時にある雑誌に、京都で舞踏の合宿がある。それが東方夜総会。軽いノリで行ったんですよ。「京都で観光旅行しようかな」くらいの。
行ってみると、鞍馬からさらに1時間くらい山奥。車で迎えにきたんです。ボロボロのバンで。頭剃った人が。電気もないような古い民家で共同合宿。変なバーレッスンとか共同作業とかさせられて、三日目に頭剃られて、眉毛剃られてみたいな。いつの間にか、どんどん。なんかさらわれていくような体験だったですね。
伴戸:その前に舞踏の公演を見て、おもしろいなと思った経験は?
由良部:ないですね。本当に軽いノリで。何日かめに、白塗りさせられて、裸になって、森の木にぶらさがって、写真をバチバチとられてみたいな。「なんでー?」みたいな。
伴戸:快感があったんですか?面白そうだな、みたいな。
由良部:今まで踊りというのは技術をまず覚えて、技術を踊るみたいなイメージがあったんだけど、そのまま、自分の衝動というか情動を出すことが、踊りになるんだ、こんなんでいいんだなって。なおかつ、それが時代の先端みたいな感じだったから。「素人がやっても、全然面白いじゃん」って。自分をさらしていく気持ちよさみたいな。森ということもあるし、非日常の、それは向こうの狙いだったんだけど、非日常的なところに連れていかれて。
伴戸:何年くらい活動されたんですか?
由良部:そこは3年半くらい。
伴戸:辞められた時は、自分のソロ活動をしようと思っていたんですか?
由良部:いや。最初すごく面白い部分もあったんだけど、一種のタコ部屋みたいなところで(笑)、一つの財布でみんなが共同生活するような感じで、面白さもあるんだけど、息苦しい感じもあったり、がんばって活動するという感じなんだけど、かなりそこは野心的なグループだった。その野心的な感じについていけない感じもあったりして。本質的な部分とズレてる感じもして、自分のやりたいこととね。有名になる、大きくなることに僕はあまり興味がなかった。活動すると自分が責任を持つ立場になっていくし、自分ががんじがらめになっていくような感じがあって。飛び出したような感じで。そこは辞めると全然縁が切れちゃうんです。そこからいなくなったら、あなたはいないものみたいな。
そんな感じで。一銭も持たずに、こたつ一つ持って、真冬だったので、友達のところに。1人だけ、そこの関係以外の友達いたんです。
伴戸:そこから自分の表現を考えていこうという思いはあったんですか?
由良部:2年間くらいは何かやるという気にならなかったんですが、いろんな本を読んだりして、今までやってきたこと見直すというんですかね。僕は東方夜総会の活動の中では、外から来た人の稽古をする担当だったんですよ。それで、表現と日常の稽古が乖離している、日々やることというのは、バーレッスン。バレエのバーレッスンを変形したようなものとか。どこかから借りてきた踊りの練習をするとか。表現では新しい取り組みはしているんだけど、日常においての身体の使い方は、「何してるのかな?」って感じで。自分にとって、もっと根っこから掘り起こしたいみたいな思いはあったかもしれない。
伴戸:由良部さんが東方夜総会を辞めた後、部屋の銀色のアルミ箔を張りつめて生活しておられたと、昔に聞いたことを思い出しました。本当ですか?
由良部:窓ガラスにワイパーつけてね。(笑)
伴戸:なぜ?
由良部:ワイパーが好きだった。(笑) しばらくワイパーに取りつかれていた。
伴戸:由良部さんの踊りを見るまで私の舞踏のイメージはカクカクして、型で動いていくというのがあったんですが、由良部さんの踊りは流れるように踊られる。「これも舞踏なのか。何をもってして舞踏というのかな」と思いながら、由良部さんに踊りを教えてもらうようになったのですが。
東方夜総会はどちらかというと、型で動くイメージだったのではないかと思うのですが、どういう変遷があったんですか?
由良部:自分のやりたい踊りを見つける過程なんだと思うんですよね。僕はもっと日常の身体のあり方とか普通の稽古とかからしたいというのがあって、あまり表現そのものにそれほど、大事なんだけど、それが一番じゃない感じがあったんですよ。舞踏の場合、身体のインパクトというんですかね、それ自体の存在感というかインパクトを与えようとする感じがある。僕もよくやらされてたけど、見るからに痛そうとか、例えば、僕がやった踊りで、銅のお皿があってね、こんなに大きいの、3人の男が歯に加えて引っ張り合うような感じ。ちょっとこうすると(引っ張るような)、歯がボリッといってしまうような感じだから、動けるか動けないか、みたい。踊ってる方はイヤでイヤでしょうがない。見てる方は「面白い」とか言うわけ。それとか、洗濯バサミを身体中に百個くらいつけて。
伴戸:ナマで?
由良部:ナマで。それが時間がたてばたつほど、痛くなる。腫れてくるわけですよ。それを二人でいじりあって。本当に「痛いっ」みたいな感じで。そういう踊りをして、本人は踊ってるって感じじゃなくて、リアリティみたいなものを見せるような。もちろんそれだけじゃないんですけど。そういうものが結構多くて。どうもそれは面白いのかもしれないけど、日常的にそんなことやりたいわけじゃないし。というような意識があって、表現じゃない、身体の使い方とか、そういうものに興味が出てきた。
伴戸:使い方というと、例えば?
由良部:いっぱいあるんだけど…後にしようか。
伴戸:ALS-Dが始まったのは何年からでしたか?
由良部:ちょっと説明しないといけないんだけど。僕の知り合いの甲谷さんという人、20数年間の僕の知り合いなんですけど。ALSという病気になって、ALSというのは筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)といって、最近ドラマにもなったので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんけど、全身の運動筋が全部失われてきて、最終的には呼吸筋も失われるので、人工呼吸器をつけるかつけないか。よく安楽死の問題で、必ず取り上げられるような病気なんですね。彼は指圧師でもあって、武道家でもあって、ヨガとか、身体のスペシャリスト。
彼とはいろんな話をしたんだけど、彼はいつも僕に対して、踊りって面白さとか表現部分があるとしたら、彼の場合は、武道とか治療というと、効くか効かないかが大事なわけじゃない。面白いか面白くないかじゃなくて。動きがどういう意味があるのか。ある種の客観性みたいなものを、いつも突きつけられるような感じの人間であって、僕にとっては。身体のスペシャリストのような人間がそういう病気になっちゃって、彼はある時、こういう病気になったけど、病気になってからの身体の知覚力は昔の数十倍になったと言っても過言ではない、みたいな言い方をしたりして。病気になりながらも前向きというか。僕らはボランティアでサポートしていて、まあ、これだけ話しても2時間くらいかかっちゃうんだけど。
サポートしながら、彼の独居スペースと僕の稽古場が一緒になってるんですよ。ALSという難病の場を開いているというか。普通は閉じちゃうんだけど、開いて、なおかつ、踊りというか身体、ALSも一つの身体というか。彼は「ALSという身体を踊っている」と言った。ブログの最後の言葉がそうだったので。今は会話も、意思疎通ほとんどできなくなっていますけど。最後にブログで言った言葉がそうだった。ALS-Dというスペースで、一緒に。僕も半分ヘルバーしながら。
伴戸:その様な活動の為、一時は、舞台というか、踊る機会が少なかったんじゃないですか?
由良部:表現的な部分ってね、追われちゃうじゃないですか。もうちょっと日常からの身体というのも含めて、どういう稽古していくかということはずっと頭にあったんですけど。それと彼のように随意的な動きが、まばたき一つできないような、ある種、下手なダンサーより全然リアリティのある身体というんですかね、そういうのに向き合っていく中で、自分自身は彼を助けてるというよりか、ある種の身体という問いを彼と共に向かい合っているという感じなんです。
伴戸:最近はWSも頻繁にやられてますよね。
由良部:WSというより稽古。
伴戸:週に2回くらいは。
由良部:定期的なものは3回やってますね。
伴戸:長い間、私も20数年前に教えてもらって、ずっと舞踏を、どう踊っていくかを考えてこられたと思うので、その辺りを。お渡しする感じで。
由良部:「舞踏って何ですか?」と言われる時があるんですけど、「カラダを踊る」こと。「カラダで踊る」じゃなくて。「カラダを踊ることが舞踏です」みたいな言い方をしているんですけど。
「カラダで踊る」というのは、身体を道具として何かを表現する。僕の主題、テーマ自体が「カラダ」なんですね。身体を用いて、何か違う主題のことをするんではなくて、カラダ自体がいつもテーマ。常にそれは変わらない。いろんな(作品の)題名とかイメージがあったとしても、結局はカラダ自体がテーマなんですね。そういう意味では「カラダを踊る」なんですけど。
日本語で身体を表す言葉がいっぱいあるんですね。身体(しんたい)、体、肉体、からだ、カラダ。こう書くと微妙にイメージが違いますよね。身体(しんたい)というと、対象的というか。見たもの、構造的とか、そんな感じがするんです。対象としてあるからだ。肉体はどんなイメージしますか?
参加者1:裸な感じですかね。
由良部:ちょっとセクシャルなイメージ。精神と対立しているというイメージがあるじゃないですか。精神と肉体。精神からこぼれ落ちた何かみたいな。頭で統御できないイメージがあるので、セクシャルなものと結び付いて。「肉体の門」とか。知ってる人少ないか。
「からだ」と平仮名で書くとどんなイメージします?
参加者2:身体測定みたいな。
伴戸:小学校の。
参加者2:そうそう。小学校の、そういうイメージ。
参加者3:保健とかで使うイメージ。肉体というと美術とか美学とか。
由良部:他にイメージありますか?
参加者4:生まれたままの姿。
参加者5:からっぽとか。からっぽの感じ。
由良部:いろいろなイメージ。別にこれは定義できるわけじゃないので。僕の中では、平仮名で書くと、気持ちを含んでいる。想いとかも含んでいる。ちょっとやわらかい感じ。
最近、僕はカタカナを使っている、使わざるを得ないという感じなんですけど、これを使うと謎めいてくるんですよね。「どこからどこまでがカラダ?」みたいな。対象としての身体というより、こういう字とだぶるんですよ。「空」の「誰」。空っぽなんだけど、誰? あんた誰なの? このカラダって何者なの? そんなイメージがだぶってくるんですよね。
カラダといった時に、それは対象としてカラダではなくて、ある意味、僕の中では全部カラダなんですよ。床もカラダだし、天井もカラダだし、青空もカラダだし、お皿だってカラダみたいな。ちょっと変なこと言ってるんですけど、境目がないんですよね。見てる私と見られている何かとの、境目がなくなる感じ。それも含むような。
赤ん坊の身体性で思うんですけど、今、ここに僕らがいて、「私がいてあなたがいます」っていう風に、ここに(私)中心があって、対象(あなた)として見るじゃないですか。すごく当たり前って感じで、「それが宇宙だ」みたいな。どこまでいってもそれしかないじゃんみたいな。私がいて、どこまでいっても対象が、まわりに広がっている。
赤ん坊の時はそういう風に感じてなかったんじゃないかな。赤ん坊の場合は見てるもの、聞いているものと未分化な状態で、むしろ食べてるような感じ。見てても、そこにある光りも、食べてるような感じ。同化、吸収しているような感じがするんです。自分の身体、まるでここにある光り、この指と、空間と、全部自分の食べ物みたいな感じ。全部が同化、吸収する何かみたいな感じだったんじゃないかな。全部が食べてるような、そこにあるもの、そこにあるもの、全部が食べ物。それがいつの間にかギューっとして、そこに自分が現れて、「私がここにいて、対象がある」みたいな。全部が食べ物で、全部同じもので、同じ身体で、同化・吸収する何かで。そうなんじゃないかな。そんな感じがするんですよね。
私が現れた瞬間に、今まで食べていたものが外側に押し出されて、モノとしてあるような。言うなれば、手袋が裏返された宇宙みたいな。今まで全部自分だったものが、外側から内側に全部包んで食べるような感じが、全部の外側がキューとここに柱みたいに立ってるんです。逆に全部それを押し出して、一種の対象として。すごく大雑把な言い方だけど、何かそんな感じがするんです。
僕らがこういう風に、「私がいて、あなたがいて」という感じ方自体が、ある身体のあり方の一つでしかなくて、僕らは例えば、赤ん坊の時、もしかしたら、これから死んだ時の身体というのを考えるとね、いろんな宇宙的な変容の中にあって、今こういうような意識もすでにある身体のあり方でしかない。なぜなら、「私がいて、対象がある」というのは同時に生まれるんですよ。私だけがいて、対象がないっていうことはないし、対象だけがあって、私がないという世界もないんですよね。私という中心があって始めて、対象がうまれる。そういう風な「カラダ」なんですよね。謎な。僕の言いたい「カラダ」って。
そういう「カラダ」を踊る、なんですけど、主語が分からない。「私」が「カラダ」を踊るんじゃないんですよね。主語って表しようがなくて、「カラダ」の中に「私」が生まれるような感じがするんですよね。「私」が運動するんじゃなくて、「私」が「カラダ」を動かすのではなくて、むしろ、「運動」の中に「私」が表れる感じがするので、主語が謎なんですよ。
舞踏の歴史というか、最初の方ですね。身体を踊るということにおいて、リアリティというんですかね、すごく痛い身体とか名づけようのない身体、異形の身体。そういうあり方、一種のオブジェのような。オブジェという考え方、これはペットボトルではなくて訳の分からないもの、名づけようのないものとして表すということですよね。身体もそういう感じ。表現として。その時代はありとあらゆるところで、美術なり音楽なり文学なりにおいて、美術で何かを作るというより、美術そのものを問うというか。音楽そのものを問うていくという運動がすごく盛んな時代。それ自体を問うということは、今まであった権威を疑わざるを得ないわけです。描くこと自体を描くとかということになってくると対抗的。権威を過激に否定していく運動とも結びついてくる。50年代60年代、非常にそういう動きが過激にあって、舞踏もその中の一つであることは間違いない。今までの踊るということ自体をもう一回見つめてみる。今まで鍛え上げられてきた、「これがいい踊り」というのを、もう一度見つめてみると、身体自体が情動を表すような、それ自体がリアリティになったりとか、裸でごろんと転がって胎児みたいにピクピク、「それがいいよ」みたいな感性というか。そういうのが舞踏の始まりに多かったです。
だけどもちろん、身体はオブジェにもなりきれないので。なぜなら日常があるじゃないですか。日常生きてることもあるし、オブジェにしようとしてるのも自分、ある意味身体だし、身体ということを問うということは、表現のためだけに終わらないわけですよね。美術を美術するというと、素材を問うというのがあるかもしれないけど、身体を問うということは、もうちょっと大きな謎になってくるんですよね。僕は「身体って何?」ということをすることが、僕にとっては舞踏、と言ってるんです。
そういう意味で言ったら、土方さん、大野さんを軸とした流れだけではなくて、もっと大きな流れがあるんじゃないかな。いつも言うんですけど、まだ端緒についたばかり。この謎はまだまだ始まったばかりで、全然解けてないというか。最近、笠井叡さんが「カラダという書物」という本を出されましたが、身体という書物を読むことが踊り。全くそこらへん、僕は同感するんだけど。「書物」という言葉は、ちょっと違うかなという気もするけど、まあ、そういう風な大きな流れで言うと、そんなことを思いますね。
まだ大丈夫かな。
伴戸:大丈夫です。ちょっと口をはさむと、私が由良部さんと稽古を始めた時に印象に残っているのは、「身体は未知なものや」ということをよく言ってはって。その頃、私は身体はいつも一緒にいるものやし、そんなに未知なものって思ってなかったんやけど、「謎なもの」と言われて、そういう風に身体を見ていくことが舞踏なんだろうなと思いました。
由良部:身体って本当に不思議なんですよね。自分のもの、所有物だと思うと、つまらない、もっと身体を脱ぎ捨ててみたいな。
よくこういう例を出すんですよね。砂浜でお城を作るじゃないですか、そうすると波がバサーバサーと、だんだん崩れてくるでしょ。身体って、バサーバサーと波にさらわれても、ずっと残ってるわけですよ。
伴戸:残ってる?
由良部:身体がね、なおかつですよ。波とか砂が取り入れながら、中身がすっかり入れ替わりながら、なおかつ城が残っているわけですよ。僕らの身体もそういう外からの力にさらされているわけですよ。さらされながら身体は保っている。砂浜に常に浸食されるような力を取り入れて、中身は全く入れ替わるわけですよ。砂粒や水分とかは、全く入れ替わるんだけど、お城がそのまんまなんです。僕らの身体は全くそうですよね。ずっと維持してるじゃないですか。少しずつはもちろん変化してるけど。それを「動的平衡」という言い方する人いるんですけどね。動きながら平衡状態を保つ。非常に不思議。何がこの身体を維持しているのか。僕の中では、いろんなものありますよね、食べたり出したりして。それを成り立たせている力、坩堝っていうんですかね、エネルギー流そのものの方がむしろ身体って感じがするんですよね。僕らは城そのものを身体って思うわけですよ。お城の形がね、保たれている形が身体と思うんだけど、それだけではなくて、周りにあるどんなエネルギーが身体に流れ込んでいるかということの方が身体、身体に近い。それを「虚の身体」という言い方するんですけど。あるいは「呼吸体」。
伴戸:それは気の流れみたいなものですか?
由良部:気というとちょっと曖昧な感じがあるんだけど。それがどういうものか、今日は三つほど、どういうエネルギーが流れ込んできているか、ご紹介しようかなと。
対象としての身体ではなく、我と我が身の身体、どういうエネルギーが流れ込んできているかということ。大きく三つ言うと、一つは「重さと軽さ」。二つ目は「知覚の力」ですね。聞いたり見たり、知覚していく力。もう一つは「時間」。その呼吸をまさに我々の中に流れ込んでいる。一種の呼吸をしている感じがあるんですね。それが僕の中の大きな探究、日々の稽古の中の大事なことなので、ちょっと説明しながらやってみようかな。
まず「重さ」ですね。結構人間って重心を常に変えてる。下の方にあったり、ちょっと考え事してる時に、パーッと上の方にいったり。いろんなところに自分の重心みたいなのが移る感じですね。赤ん坊の時から立ってきたんですけど、立つことでバランスをとる。バランスをとりながら世界を覗き込むような感じで、バランスを常に保つ。日常の中で当たり前のようにしているんですけど、重心、バランスを保つということは非常に不思議な感じがして。踊りでも中心、バレエなんかだと上の方に持ち上げる、能だと腰に下げたりしますよね。そういう風に、上にあげたり下げたりというのは、音楽的な感覚と似てますよね。低い音を下に感じたり、高い音を上に感じたり。音楽的なものと似てると思うんですけど。踊りの中で軸を作るというのは非常に大事にするんですけど、軸を作ってターンするとかね。僕の場合は、軸もあるんですけど、由良部流バーレッスンというか、バーを使うわけではなく、バーレッスンって基本のようにやるじゃないですか。これは軸をピタッと作るような、何十年もやるんですよね、バレリーナの人は。
僕の場合は、腰を抜くんですよね。どういう軸かというと、抜いて。どういう感じがしますか? 抜いてしまって、固定するところが一つもなく、なおかつこことここを結んでいるような感じにすると。一つはね、ここで私が立つ、重心を上げる下げるすると、この中の移動って感じ。この感じが、イメージ的に言うと、まわりがどんどん軽くなるので、手が上がっていく。空間が重くなるので、下がっていく、感じがするんですよ。身体よりも周りの方が重要になってくる。周りと一緒に動いていく。周りのものが動いていく。力も使わず天地を動かす。そんなイメージ。身体を動かすんじゃなくて、周りが軽くなるから手が動く。全体を動かすような感じになってくる。そうすると、身体はそれが通る…なんて言うのかな、空間の軸みたいなイメージです。身体の軸を作るんじゃなくて、空間の軸を作る。重い感じと軽い感じ。簡単そうで難しい。
伴戸:みなさん、やってみられますか?
由良部:だいたいみんな腰が抜けない。立つんですよ。最初のうち。
伴戸:寝かすというのは、こういう…
由良部:全体がね。全体がつながる感じだから。どこにも滞ったところがない。頭から仙骨、仙骨までいって、足先から拇指球のあたりが中心。拇指球と上の軸を結ぶんですよ。ピターッと。それが一つ、由良部流バーレッスン。
伴戸:自分の軸を作るんじゃなくて、空間の軸を作る。
由良部:身体はむしろ抜いていく。いかに抜けるか。力を抜いて、一番リラックスした状態。なおかつ背骨全体がどこも滞らない。だいたい入れることは教えられるんですよ。「腰を入れなさい」みたいな感じは多いんだけど、抜くことができると入れることは造作もなくできる。入れることばっかりやってると、抜くことができない。僕の感じで言うと、抜く方が基礎的。僕にとってはすごく大事で、重さと軽さという意味では、抜くということが重要。抜かなければいけないってことじゃないです。
伴戸:由良部さんが「カラダ」を考える上で、そういうやり方、抜くことで見えてくるものがあるということですね。
由良部:常に重心が移動するんですよね。例えば、こういう動き、水のような動き。これって重心が移動するんですよ。どこにも滞らない。運動の中に重心が溶け込んでいくような。身体の中に常に重心が溶け込んでいくように思うと、こういう水に。例えば、水のようになって、ヒューっと。そうすると立っている力をこぼしていくわけですよ。立つ時にこぼしたものをもう一回集めて、広いあげて。これを保持する、立つという力の中で。
動物でこんな動きするものいないですよ。多分。動物って割と固定してるんですよ、重心が。ペンギンが立つっていうけど、すごく下の方で。立つという中で常に重心が。こういう風に水の動きは常に重心が移動しています。
これをもっとすっと上げると、こういう動きになるんです。水のようなものをここ(胸)にあげますね。そうして、ここから開くように動くと、空気のようになるんですよ。水の動きは重心が動きとともにあるんです。空気、大気になると、膨らもうと外にいきたくなるのね。まるでここから声がふぁーっと出るように。さらに上がると、身体から抜けちゃうんですね。光をイメージすると、重心がここまでで限界だとすると、さらに上がると、向こうにいっちゃう。身体から分離しちゃう。光のイメージ。
今度は下げますね。これは物質のイメージ。物質をイメージすると、身体より下にいっちゃう。身体を支えているものでしかなくて、重さの重心はもっと下の方に、実体が、ここらへんに重さの実体をイメージすると、物質的な感じ。物質的になるにしろ、光になるにしろ、身体を越えちゃうんですよ。この身体。なんとなく分かります?
物資をイメージするのと光と。その中間の広がりの大気と水の動きは、水は一番身体とともにあるんです。大気をイメージすると、広がりの中にふぁーっと自分の身体が。水になると、身体が動きとともにあって。抜けると、身体と分離しているような、支えているような何かね。実体はもっと下の方にイメージする。光の中に入るようにイメージすると、実体をこっちの方にイメージしないと入れない。
多分、一年くらいやらないと、身体でなんとなくイメージをつかむのに、全然分からないかもしれないです。身体で理解するということと、頭で理解することは違うから。
伴戸:言葉だけで説明しづらいことだと思います。やってみると、また違う感じがあるでしょうけど。
由良部:まあ、そういう感じで、重さ、重力と浮遊力、光としましょうか。そういう風なものを身体が呼吸していく。
伴戸:変わっていくということですか?
由良部:そのエネルギーの中に身体がある。もう一つ、知覚ですね。これも常にあるじゃないですか。常に見たり聞いたり。僕ら、どちらかと言うと、知覚というのは情報だと思っている。情報を受け取って。「そこに何かがある」。それをエネルギーとして、見ることをエネルギーが出て入っていく。エネルギーそのものの体験として、あんまり感じない。情報として捉えると、すごく疲れてくる。むしろ、知覚行為というのは、その中にあるエネルギー、つまり、見るってことを、こっちから出ていくエネルギー、あるいは、向こうから入ってくるエネルギー。
ババッと言ってしまいますけど、知覚は五感と言いますけど、僕はそういう感じはしないんですね。見る、聞く、匂う、味わう、それぞれ全然違うんですけど、触覚というのは中心にある。中心にあって、四覚が周りにある。触れるということは一番なぞめいているし、よく分からない。だけど、触れるは一番中心にあるような感じで。つまり、触れてることは触れられていること。触れてることと触れられていることは同時に起きるんだけど、一種の呼吸みたいなものがあるでしょ。例えば、ちょっとイヤな人と身体が隣にいると、「触れられている」って、ちょっと離れていくような感じ。リラックスした場になると、自分がそこにふぁーっと触れていくような感じってあるでしょ。全ての知覚をエネルギー体験として。それぞれ違うんです、全然。だけども、エネルギー体験として感じる。その中心がどこにあるかというと、胸の方に。こう手を上げるじゃないですか。全部、皮膚も全部、触れていく。触れられていくと、全ての皮膚を通って、すーっと胸の奥に入っていく。それがもう一回出て、中心から出ていく。なんかそんな感じです。これが知覚の呼吸。これを新鮮なエネルギー体験として感じることは、ごく稀で、いつも情報として、判断としての知覚になってしまうと、非常に疲れるじゃないですか。
見ること自体が、本当に壮大な風景に、自分がその中にふぁーっと入っていくような感じ。そんな知覚体験。それが常にあるわけですよ。知覚するエネルギーが。
もう一つは時間。時間を作っているのは、どこかと言うと、明らかに頭です。明らかにじゃない?
(一同笑)
胸とかお腹で時間を感じられないじゃないですか。
伴戸:そうなんですか。
由良部:つまり時間は、昨日を思い浮かべる、さっきここに入ってきたことを思い浮かべると、どうします? どうやって昨日が思い浮かべられる?
参加者:記憶
由良部:記憶は何かと言うと、知覚? 昨日のあなたに触るように触れます? 触れないですよね。知覚とちょっと違いますよね。イメージ、像でしょ、簡単に言うと。実体じゃないです。頭が像化するわけです。頭の中で像化する力があるので、時間を感じられる。昨日であろうが、2,3秒前であろうが、時間として、過去として捉えると、像化する力が、まさに私たちの身体がイメージを作り出す力がある。イメージを作りだしながら、なおかつそこに、自分の意志を込めて「明日あそこに行くぞ」と思った時に、明日があるでしょ。像の中に自分の意志を込める。像がないと。時間は常に像じゃないですか。実体じゃないし、知覚じゃないし。重さや軽さ、知覚のようなものでもないし。常にそれを行っているんです、僕らが。像を作り出している。それを、時間の呼吸と呼んでいる。像を作っていく力。
これは頭部で。知覚は胸で。重力は縦軸。
重さと軽さが呼吸してます。知覚が呼吸するときはこっちが中心。胸を開いて、どこまでも開いて、胸のどこまでも奥に入っていきます。これ緊張したらダメですよ。どこまでも吐く時にやわらかく。それをこっちに入れるんです。次は、頭。ここに立っていながら、あなたはすでに幻である。想い出と化していく。頭の力に集中すると、そうなっていくわけです。頭の呼吸と。分けるとね、一応、そういう風にできる。重力と知覚と時間は、非常に今まさにある。今まさにここに働いている力、我々の中に。普段は入りまじりながら、ごちゃごちゃしちゃうんですよね。それを一応分けて、大きく大きくしていくんです。そうすると、いろんな形でエネルギーが、この中で、身体の中にあるエネルギーが流れていく。虚の身体というんですかね。身体は、重さや光、様々なモノが通過していく何かみたい。
伴戸:日常生活の中では、普通に呼吸としてやっているけれど、呼吸を細かにみていけば、例えば、こういうものがあって、ただ単に酸素を吸ってだけじゃなく、エネルギーというものが出たり入ったりしているという感じ。
由良部:時間がなくなっちゃった。どうしよう。ちょっと踊ろうかな。
-その後10分ほど踊る-
伴戸:時間が少ないですが、質問などあれば。
参加者:由良部さんの動きというのが、ずっと前から、そういう動き、方法を確立されていたということが分かったんですけれど、そういう理論、技術に基づいていたんだなと、あらためて、見せていただいて、驚いたんですけど。ご自身でこういうものが踊りの原理だと感じたのはいつぐらい? どんなきっかけですか?
由良部:3つだけじゃないんですよ。いまだに試行錯誤していて。20年くらい前から教えてたよね。その頃、ワークショップやりだしたんですよ。「何を教えられるのかな」というのが自分であって。「教えてほしいと言われても、教えることあるかなぁ」って。
伴戸:最初は、自分がやっている練習があるから、それを一緒にやるんやったら、やってもいいって。そのうちに、当番制にしようって言い出さはって。「僕は教えるという関係性は嫌だから」って。私たち、習ってるつもりやけど、当番とかふられて、今日のリーダーとか。でも、やったら、「それはね…」って突っ込まれる。
今、言われたように、踊り自体、踊りのエッセンスは、20年前、最初に由良部さんを見た頃から、そういう動きをやったはったので。動きの中にあるものは何だろうと考えていかはったんですか?
由良部:そうそう。どっちかと言うと、踊ってるときに、自分の中で、「この動きって何なんだろうな」って思うわけですよ。無意識にやるじゃないですか。「これって何かな」。それをもうちょっと拡大するというのかな、他と関連付ける、もっと大きくしていく。そういう作業ですね。ないものを作り出しているんじゃなくて、あるものを、訳が分からないけど、少しずつよりわけていくというと変ですけど、エネルギーのあり方を見つけていく。試行錯誤しながら。要するに、自分だけの思いじゃなくて、教えるというときに、客観性というか、誰にとっての身体、自分がよくても、「あんた、どうしてできへんの?」じゃなくて、どの身体にもあるものじゃないといけないというのがあって。その中で、最初の頃は本当に教えるのができるのかなって感じでやりながら、でも、なんやかんやで、そういう立場になったりとか。15,6年前からワークショップって、海外行ったら、それが付き物みたいにやるようになって、「何教えたらいいんだ」みたいな中で、表現というより、もっと原理的、もうちょっと誰にでも、表現者じゃなくても、身体を持っている限り与えられるものって何だろうっていう感じで。それも思いつきとか主観的なものではなくて、もっと確かな手ごたえみたいなのを探したいわけですよね。その中で探してきた。
参加者:面白かったのは、すごく普遍的な、時間の考え方とか知覚の考え方とかというのは、普遍的な考え方だなと思う一方で、そこから出てくる動きは由良部さんの動き。たおやかな。
参加者2:音楽、バックミューッジックに関して。ずい分、昔から活動を見させていただいて、音楽が変わっていってらっしゃるように感じているんですけど。私の友人の作曲家がスタジオに寄せていただいて、ダンスを教えていらっしゃるときの音楽もまた、今日の音楽とは違い、音楽に対して、リクエストされることは何かありますか?
由良部:音楽家ということですか?
参加者2:表現されるにあたって、バックグランドとしての音楽です。
由良部:割りといろんな音楽。確かにいろんな曲をやるんですけど、音楽と身体っていろんなあり方があって、それこそ音楽の中に入っていくような動き方があるし、音楽を背景において、その中を動いていくようなあり方もあるし、音楽をまるで忘れていく、食べていく、細胞一つ一つに降り注いでいくようなあり方とか、音楽とのいろんな距離感があるんです。音楽とは一種の出会いですね。どういう風に出会えるか。
参加者2:例えば白石さんというDJが音楽を流されているときに、今の踊りとはずい分違ったように、私は感じたんですが、DJや選曲家の方にイメージを言葉で伝えることは可能なのか。ミステイクすることはあるのか。
由良部:多分、あまり言葉で言っても、伝えるの、難しいんですよね。白石さんは何回もやってるから、いろんな音を流していく中で、多分彼も観察しているんだと思うんですよ。音の中でどういう風な動きをしているのかって。その中で彼が音世界を作っていくと思うんです。いかに身体の中に通過していくかってことですかね。無音というのもあるじゃないですか。多分、無音がいきるような音がいいかな。無音はないわけじゃない。逆に言うと、無音は音楽の可能性そのものかもしれない。それが感じられるようなものがいいかな。音楽の沈黙というんですかね、そういう部分が際立つような感じ。逆に、それは音楽の豊潤さでもあるし、それがあればあるほど、沈黙みたいなものが際立っていく。
参加者2:そういうものを好まれるわけですよね。
由良部:あんまり拒否はしないんですけど。これはしたくないとか。なるべく、なんでもやるんですけど。でも、やっぱりありますよね、「これかー」みたいなときもあるし。